1.降雨量
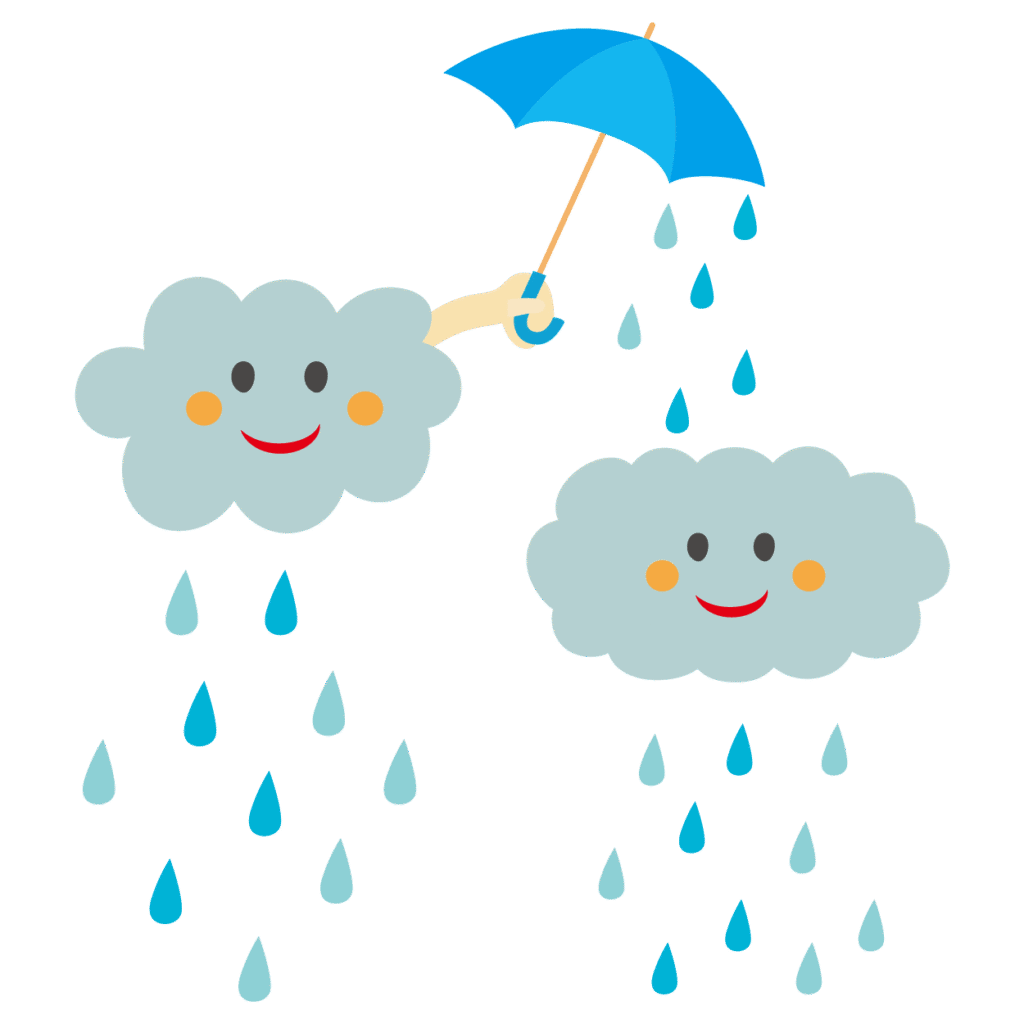
特別警報、線状降水帯、記録的短時間大雨情報、危険を知らせる異常気象ワードは、当初は驚きを持っていましたが、今は慢性化してきました。いつどこかで事故や災害に巻き込まれても、不思議でない時代になりました。
2004年新潟・福島豪雨災害を受け2005年水防法改定により洪水ハザードマップの作成が義務付けられました。前提となる河川整備に用いられる計画降水量は、多摩川ですと年超過確率1/100でした。
2015年水防法が改正され、想定降水量が河川整備に用いられるものから想定し得る最大規模の降雨量(「想定最大規模降雨」という)に変更されました。要素となる「降雨継続時間」は、今までの洪水時又は雨水出水時の降雨の状況及び流出特性等を総合的に勘案して定め、総降雨量は全国を15地域に分け、地域別、面積別及び降雨継続時間別の最大降雨量から地域特性を考慮し、年超過確率1/1000よりも低くなるようにすることができるようになりました。(浸水想定(洪水、内水)の作成等のための想定最大外力の設定手法)「国土交通省ウェブサイト」
多摩川の想定最大規模降雨は、2日間総雨量588ミリメートルです。
2.避難経路
水防法改正後、2015年9月鬼怒川決壊のあった関東・東北豪雨災害が起こりました。ヘリによる救助者数 1,339人、地上部隊による救助者数 2,919人。既存のハザードマップでは、適切な避難行動につながりませんでした。
住民への周知・伝達がテーマになりました。
3.水防法に基づく洪水ハザードマップ
国土交通大臣または都道府県知事は、下記①~③の河川について、洪水浸水想定区域、洪水ハザードマップの対象とします。
①洪水予報河川及び水位周知河川により指定した河川「国土交通省ウェブサイト」
②特定都市河川浸水被害対策法により指定した河川
③都道県知事に委託される区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきもの及び二級河川として国土交通省令で定める基準に該当するもの
そこに指定の区域、浸水した場合に想定される水深、浸水継続時間に加え、市町村の長は、洪水予報等の伝達方法、避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項、避難訓練の実施に関する事項、要配慮者利用施設などの施設名及び所在地、その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を住民等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければなりません。
4.東京都の洪水ハザードマップの公表状況
東京都の各区市町村の洪水ハザードマップの公表状況はこちらです。「東京都ウェブサイト」
東京都の浸水リスクの公表状況はこちらです。「東京都ウェブサイト」
1000年に1度の想定ですが、イメージがあれば、いつどこかで事故や災害に巻き込まれても大丈夫です。